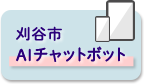子どもたちのSOSに気づきましょう
子どもの様子に注意してください

4月から新年度がスタートし、入学や進級で自分自身を取り巻く環境が変わり、そこから夢中になって過ごした今、お子さんはお変わりなくお元気ですか。「学校に行きたくない」「習い事をやめたい」と言うようになっていませんか?
子どもにとって環境が変わる時期だからこそ「その環境に慣れないといけない!」と焦りを感じ、ストレスを抱えてしまう場合があります。環境に慣れることは大切なことではありますが、心配な面もあります。我慢して不調を自分自身で誤魔化してしまうことも少なくありません。我慢しすぎた結果、気力体力の回復が難しくなってしまう可能性もあります。
「最近、子どもの様子がおかしいな・・・」と感じたら、それは子どもからのSOSかもしれません。子どものSOSに気づき、適切に対応することで、子どもたちの「いのち」と「こころの健康」を守ることができます。
子どものSOSとは?

子どもたちは強いストレスにさらされると、大人とは少し違った反応を見せます。特に子どもの年齢が低いほど、自分の中で何が起こっているのかわからなかったり、気持ちをうまく伝えられず、からだや行動で表現することが多くなります。
次のようなサインが続いていたら、子どもたちに声をかけ、話を聞いてみましょう。
からだの不調
- 元気がない、体がだるそう、疲れている、顔色が悪い
- 頭痛や腹痛、めまい、吐き気
- 夜尿(おねしょ)、お漏らし
- 食欲がない、食べ過ぎる
- 眠れない、なかなか起きられない、寝すぎる
行動上の変化
- 落ち着きがない
- いつもよりワガママになる
- 赤ちゃん返りをしたり、甘えた言動が増える
- イライラしていたり、ケンカが増える
- 学校に行きたがらない
- 友達と遊ばなくなった
このような変化の背景には不安が隠れていることを理解することが大切です。大人が子どものSOSを冷たく突き放すと、不安はもっと大きくなって、反応はさらに複雑になってしまします。
SOSに気づいたら
声をかける
子どもの様子が「いつもと違う」と感じたら、声をかけてください。
- 元気がないけど、無理していない?
- 最近、眠れてる?
- 何か悩んでる?よかったら、話を聞かせて
傾聴する
- 本人の気持ちを尊重し、耳を傾けましょう。
- 話せる環境をつくりましょう。
- 悩みを打ち明けられたら、これまでの苦労をねぎらいましょう。
- 相手の気持ちに寄り添い、悩みを真剣な態度で受け止めましょう。
- 本人を責めたり、安易に励ましたり、相手の考えを否定することは避けましょう。
- 「あなたのことを心配している」という気持ちを伝えましょう。
つなぐ・見守る
本人の意思を尊重しながら学校の先生やスクールカウンセラー、医療機関などへ相談してください。
専門家につながったあとも温かく寄り添いながら、じっくりと見守りましょう。
子どもの「こころの健康」を守るために
1対1の時間を作る

たった10分でも構いません。子どもと向き合う時間を作ることで、子どもたちは愛情を感じ、安心し、自分自身を大切な存在だと感じることができます。
- 子どもに何がしたいか聞いてみましょう。
- 子どもが自由になんでも話せる環境を作りましょう。
- 大人も子どもに意識を集中し、一緒に過ごしましょう。
肯定的に接する

子どもは、肯定的な指示(「○○してほしいな」)を出したり、うまくできた時に褒めてあげたりするほうが、親を困らせるような態度を取らなくなっていきます。
- 肯定的な指示は、現実的な目標にしましょう。
- 子どもが良いことをした時は、しっかりと褒めましょう。「褒められる=あなたが気にかけてくれている」というのも、子どもが安心できるポイントになります。
悪いことをした時は、落ち着いて対応する
叩いたり怒鳴ったりするのではなく、落ち着いて対応しましょう。
- 子どもの落ち着きがなくなってきたら、楽しいことに興味を向けて気をそらしましょう。
- 子どもを叱る前に、10秒間止まって考えましょう。ゆっくり深呼吸をすると気持ちが落ち着きます。
- 同じことで何回も叱るのはやめましょう。
- 子どもに責任を自覚してもらうために約束を決めるのもよいでしょう。自制心を育てることにも役立ちます。
- 約束を破ったときに何が起きるか子どもに伝えましょう。その内容が現実的か、よく考えましょう。
- 子どもに挽回のチャンスをあげましょう。そして、それをしっかりと褒めましょう。
まずは自分を大切に…

自分のこころに余裕がなくては、子どもたちの「こころのケア」を行うことはできません。
規則正しい生活、十分な睡眠、適度な運動を心がけ、「こころ」と「からだ」のバランスを整えましょう。子どもが寝たら楽しいことやリラックスできることをしましょう。
あなたは独りではありません。家族や友人と気持ちを共有したり、自治体やNPOなどに不安や悩みを相談しましょう。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健センター(健康推進課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-9559 ファクス:0566-26-0505
保健センター(健康推進課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。