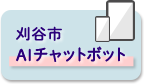井ケ谷古窯跡群出土品が愛知県登録文化財になりました
令和7年1月31日に開催された愛知県文化財保護審議会の審議を経て、下記の文化財が、令和7年2月12日付けで愛知県登録文化財になりました。
【新規登録】井ケ谷古窯跡群出土品(愛知教育大学蒐集)
概要
今回登録となった資料は、愛知教育大学の校地造成に伴い、1967年、1968年に大学や当地の研究者等によって実施された発掘調査の際に大学の校地(刈谷市井ケ谷町)に立地した窯跡から出土し、令和4年度に愛知教育大学から刈谷市へ寄贈されたものです。
その内容は、洲原第7号窯・洲原第8号窯(8世紀第4四半期)、灰山古窯・寺山第1号窯・寺山下古窯・松根第1号窯・松根第2号窯(9世紀)、松根第3号窯(12世紀末~13世紀初)から出土した須恵器(すえき)(※1)、灰釉陶器(かいゆうとうき)(※2)、山茶椀 (やまぢゃわん)(※3)です。
これらは、猿投窯(さなげよう)(※4)井ケ谷地区における古代陶器生産最盛期の変遷を把握できるもので、当地域の調査研究史上においても重要な位置を占める資料群です。
(※1)須恵器 古墳時代から室町時代にかけて日本各地で生産された陶器。土器に比べて高温焼成することによって硬質に仕上げ、色調は灰色を呈することが多いです。
(※2)灰釉陶器 灰釉(植物を燃やして得られた灰を原料の一つとして制作した釉薬(ゆうやく))を器面に施して、高温焼成した施釉陶器(せゆうとうき)。平安時代前期には国産高級陶器として受容されました。
(※3)山茶椀 中世に東海地方各地で量産された、粗製の無釉陶器(むゆうとうき)。「山茶碗」とも表記します。
(※4)猿投窯 名古屋市東郊から、旧尾張国と旧三河国の国境にかけての丘陵地帯に所在する、日本屈指の規模を有する古窯跡群(こようせきぐん)です。その内、境川と逢妻川に挟まれた猿投窯井ケ谷地区(刈谷市・豊田市の一部)では、古代の窯跡が約45基、中世前期の窯跡が約20基確認されています。猿投窯井ケ谷地区の、刈谷市域における古窯跡の本格的な調査研究は、1950年代後半から刈谷市誌の編纂や愛知用水の建設に関連して、様々な調査主体によって行われてきました。1958年には古窯跡群が刈谷市史跡「井ケ谷古窯群」として指定されています。2021年度から刈谷市によって古窯跡の分布調査が行われ、2022年に市史跡の構成文化財の追加と部分解除が行われました。




愛知県登録文化財とは
愛知県文化財登録制度は、未指定の地域の文化財に対して、幅広く保護の対象とすることと、所有者や担い手等の保存および継承に対する意識を高める目的で、令和5年度に創設されました。対象の文化財が下記の5つの種別となっています。
有形文化財
無形文化財
有形民俗文化財
無形民俗文化財
記念物
関連情報
このページに関するお問い合わせ
歴史博物館
〒448-0838
刈谷市逢妻町4丁目25番地1
電話:0566-63-6100 ファクス:0566-63-6108
歴史博物館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。