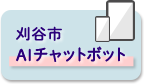医療費の自己負担割合
医療機関にかかるとき
国民健康保険の被保険者が病気やけがなどで医療機関にかかるとき、マイナ保険証または資格確認書を提示すると、医療費の一部を負担することで次のような医療を受けることができます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護(入院時の食事代は別途負担します)
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
紹介状なしで大病院の外来を受診する場合、別途負担があります。
医療費の自己負担割合
| 年齢等区分 |
年齢等区分の詳細 (各年齢に達する日とは「誕生日の前日」) |
負担割合 |
|---|---|---|
| 義務教育就学前 | 6歳に達する日以後の最初の3月31日まで | 2割 |
| 義務教育就学後から70歳未満 | 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から70歳に達する日の属する月まで | 3割 |
| 70歳以上75歳未満(現役並み所得者を除く) | 70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日まで
|
2割 |
| 70歳以上75歳未満の現役並み所得者 | 70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日まで
|
3割 |
- 70歳になると、医療機関受診時の自己負担割合や自己負担限度額が変わる場合があります。70歳以上75歳未満の人は、医療機関等でマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、所得などに応じた自己負担割合が確認できます。※令和7年8月1日以降、資格情報のお知らせまたは資格確認書に負担割合を記載しているため、これまで交付していた「高齢受給者証」は交付していません。
- 子ども医療費や障害者医療費、母子家庭等医療費など医療費の自己負担額を助成する制度があります。詳しくは「医療の助成」のページをご覧ください。
70歳以上75歳未満の人の判定基準
- 低所得者1
-
次のいずれにも該当する人は「低所得者1」になります。
- 同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税である。
- 同じ世帯の世帯主および国保被保険者の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額を80.67万円として計算。給与収入は給与所得控除後の金額からさらに10万円を控除。)を差し引いたときに0円となる。
- 低所得者2
-
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外)
- 一般
-
低所得者1、低所得者2、現役並み所得者以外の人
- 現役並み所得者
-
次のいずれにも該当する人は「現役並み所得者」になります。
- 同じ世帯に、70歳以上で住民税の課税所得《注釈1》(調整控除《注釈2》が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の国保被保険者がいる。
- 70歳以上の国保被保険者全員の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円を超える。
《注釈1》「課税所得」とは、住民税(市町村民税)の課税標準額(前年の収⼊から、給与所得控除や公的年⾦等控除等、所得控除等を差し引いた後の⾦額)のことです。
《注釈2》「調整控除」とは、基準日(前年の12月31日)時点で、70歳以上の国保被保険者が世帯主で、同一世帯に総所得金額が38万円以下の19歳未満の国保被保険者がいる場合は、次の金額を課税所得金額からさらに控除することです。
- 16歳未満の国保被保険者の人数×33万円
- 16歳以上19歳未満の国保被保険者の人数×12万円
「現役並み所得者」に当てはまる人のうち、「一般」の区分になる場合
「現役並み所得者」の判定基準に当てはまる被保険者のうち、次のいずれかに該当する場合は、「一般」の区分となり自己負担割合が2割になります。
- 同じ世帯の70歳以上の国保被保険者が1人で、収入が383万円未満
- 同じ世帯の70歳以上の国保被保険者が1人で、国保から後期高齢者医療制度に移行した人を含めて、収入合計が520万円未満
- 同じ世帯の70歳以上の国保被保険者が2人以上で、収入合計が520万円未満
上記に該当することが刈谷市で確認できる場合には、自己負担割合が2割になります。
ただし、本市で収入等の情報が確認できないときは、申請が必要となる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。